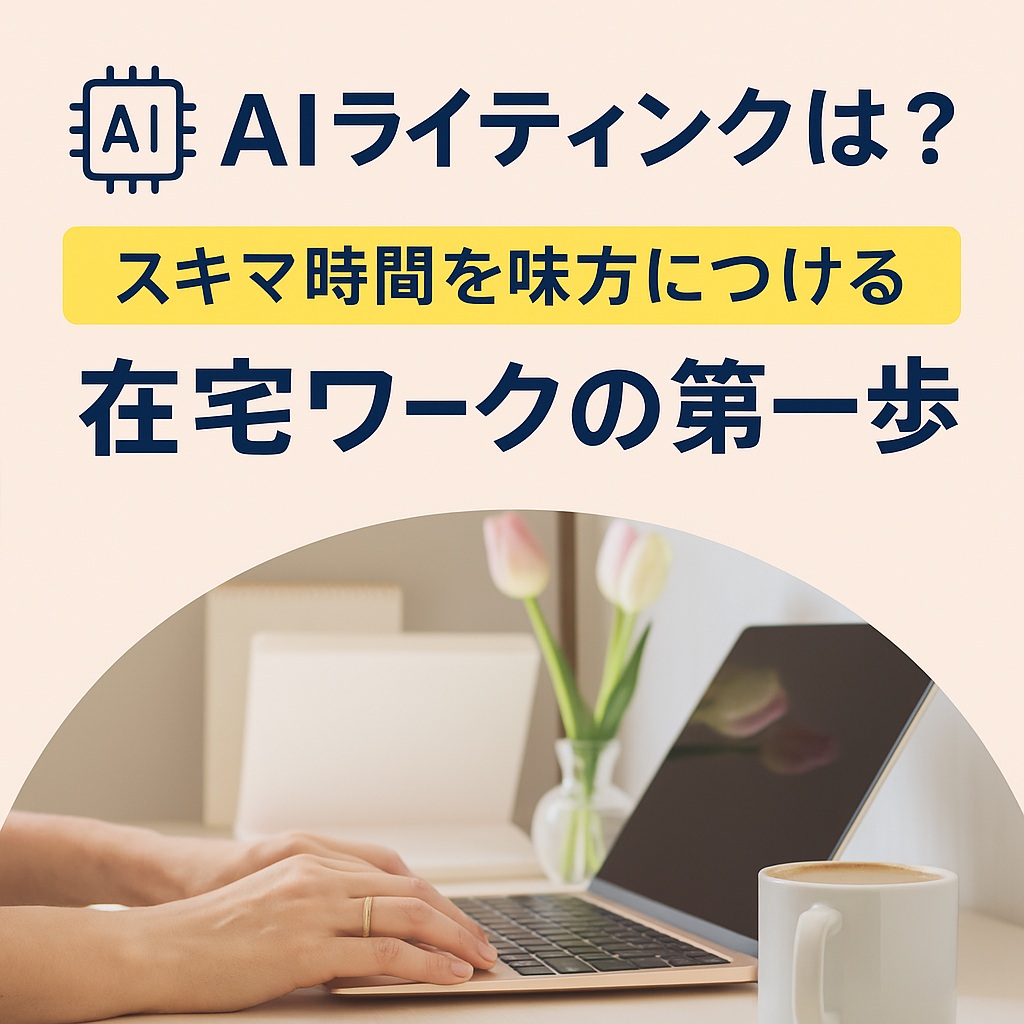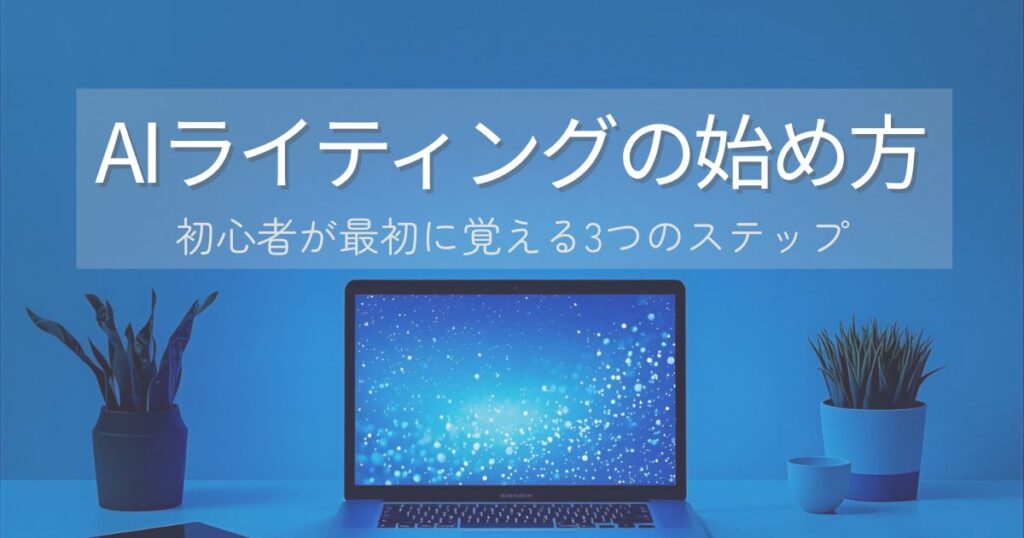
AIを使ったライティングに興味はあっても「どこから始めればいいんだろう」「ChatGPTという名前は聞いたことがあるけど、なんだか難しそう」と感じている方も多いかもしれません。
AIライティングは、専門的な知識がなくても誰でも気軽に始められます。
この記事では、AI初心者の方に向けて3つのステップでAIライティングの始め方を解説します。読み終えるころには、あなたもきっとChatGPTで“最初の1文”を書けるようになっているはずです。
AIライティングとは?基本を知ろう
最初にAIがどのように文章作成をサポートするのか、基本的な仕組みと代表的なツールを紹介します。
AIライティングの基本的な仕組み
AIライティングとは、AI(人工知能)を利用し、文章作成のサポートしてもらうことです。テーマや目的を入力すると、AIがそれに合った文章を提案してくれます。代表的なツールにChatGPT や Google Gemini などがあります。
例えば、以下のように入力してみましょう。
指示の例:AIが文章の構成や言葉選びまで整えて、あなたの自己紹介文を返してくれます。
AIは「書く補助ツール」として使う
大切なのは、AIライティングは「自動で文章を書いてもらう」ものではないということです。
AIは、あなたの考えを形にする補助ツール。アイディアを提案する、下書きを作る、言い回しを整える、文章を短くまとめる――そんな”書く工程”を支えてくれる存在です。
代表的なAIライティングツール
現在、無料で使える主なAIツールには以下のようなものがあります。
| ツール名 | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 最も人気があり、汎用性が高い。文章の練習から仕事活用まで幅広く対応 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Google Gemini | Google検索と連携し、最新の情報に基づいた回答が得意 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Claude | やわらかく丁寧な表現が得意。長文の要約やリライトにも向く | ⭐⭐⭐⭐ |
| Microsoft Copilot | Office製品と統合。WordやExcelなどとの連携に優れている。ビジネス用途に強い | ⭐⭐⭐⭐ |
初心者の方には、ChatGPTから始めるのがおすすめです。
ステップ① ChatGPTに触れてみよう
ここからは、実際にAIツールに触れてみましょう。AIツールの中でも人気の高いChatGPTの登録方法から、最初の1文を書くまでの流れを解説します。
ChatGPTの登録
ChatGPTの登録は簡単。パソコン・スマホのどちらでも行えます。
登録手順:
- https://chat.openai.com にアクセス
- 「Sign up」をクリック
- メールアドレスまたはGoogleアカウントで登録
- 届いた認証メールのリンクを開く
- 簡単なプロフィール設定を完了
AIライティングを始めるには、まずGoogleアカウントを用意しておくと便利です。ChatGPTをはじめとする多くのAIツールはGoogleアカウントでログインできます。
AIライティングを始める前に、Googleアカウントを準備しておきましょう。
登録は無料で、数分あれば完了します。
無料版と有料版、どちらを選ぶ?
ChatGPTには無料版と有料版(Plus)があります。
| 項目 | 無料版 | 有料版(Plus) |
|---|---|---|
| 月額 | 0円 | 約3,000円 |
| 使えるモデル | GPT-4o mini など | GPT-4o、o1 など最新モデル |
| 速度 | 標準 | 高速・優先 |
| 利用制限 | 混雑時あり | ほぼなし |
無料版でも、文章練習やライティングの基礎には十分です。慣れてきて「もっと速く使いたい」「利用制限なしで使いたい」と感じたら、有料版を検討しましょう。
最初の1文を書いてみよう
登録が完了したら、入力欄に試しに指示を打ち込んでみましょう。
指示の例:
指示の例:数秒後、AIが文章を提案してくれます。
仕上がりの良し悪しより、「AIがどんな風に考えるのか」を体験するのが目的です。完璧でなくても大丈夫。まずは触れてみることが大切です。
ステップ② 身近なテーマで練習してみよう
ChatGPTに触れたら、文章を書く練習をしてみましょう。自分の生活に近い題材を選び、AIとの対話を楽しみながら、徐々に指示(プロンプト)のコツをつかんでいきましょう。
自分の生活に近い題材を選ぶ
AIに慣れるためには、自分の生活に近い題材を選ぶのが一番です。
「SNS投稿文を考えてもらう」「ブログの自己紹介文を整える」「おすすめの本や映画の紹介文を作成する」など。
最初から難しいテーマを考える必要はありません。身近なテーマからAIを使ったライティングに慣れていきましょう。
効果的な指示(プロンプト)の出し方
AIには、できるだけ具体的に指示を出すのがコツです。
指示の例:⭕ 良い例:「やわらかい口調で、主婦の朝時間について簡潔に書いてください」
以下の型を意識して、プロンプトを書きましょう。
| 型 | 説明 | プロンプト例 |
|---|---|---|
| 役割 | AIに「誰として話すか」を明確に伝える(場合によってはなくても可) | 「あなたは人気子育てブロガーです」 |
| テーマ/目的 | 何について書いてほしいかを伝える | 「主婦の朝時間について書いてください」 |
| 条件 | 長さ、口調、形式などの制限を伝える | 「3文で親しみやすい口調にしてください」 「園児を育てているママ向けに書いてください」 |
AIは、伝え方を少し変えるだけでトーンや構成を自在に変えてくれます。
対話を重ねて理想の文章に近づける
ChatGPTは対話形式です。一度の指示で満足できなくても大丈夫。何度でも修正を依頼できます。
修正依頼の例:
指示の例:↓
2回目:「もっと具体的なエピソードを入れてください」
↓
3回目:「3〜4文に短くしてください」
文章を整える練習を重ねるうちに、伝えたい内容を整理する力も自然と身についていきます。
すぐ使える指示フレーズ:
- 「この文を丁寧な言葉に直してください」
- 「もっと親しみやすい表現にしてください」
- 「初心者にもわかりやすく、3つのポイントで説明してください」
- 「〇〇の視点で書き直してください」
ステップ③ 自分の言葉で仕上げて発信してみよう
AIとの対話に慣れてきたら、文章を仕上げて発信してみましょう。AIの出力をそのまま使うのではなく、自分の体験や言葉を加えることで温かみのあるオリジナルな文章になります。ここでは、AIが作った文章に命を吹き込み、発信を始めるための方法を解説します。
AIの文章をそのまま使わない
AIが作った文章は「たたき台」として使い、自分の言葉で仕上げましょう。AIの文章は整っていますが、どこか機械的で味気なくなりがち。また誤った情報(ハルシネーション=AIがつく嘘)が混じっている場合もあります。AIが出した情報は鵜呑みにせず、必ず確認しましょう。
仕上げのポイント
- 自分の体験や感想を1〜2文追加する
- 表現を自分らしく調整する
- 不要な部分を削る
- より具体的な言葉に置き換える
朝のコーヒーは一日の始まりを彩る特別な時間です。
【自分らしく修正】
朝のコーヒータイムは、一日の始まりを彩る特別な時間。
家族を送り出した後の静かなひととき、
お気に入りのマグカップで飲むコーヒーは格別です。
自分の言葉を少し添えるだけで、AI文章も自然で温かい印象になります。
少しずつアウトプット(発信)を始める
AIを使った練習を重ねたら、少しずつアウトプット(発信)を意識してみましょう。いきなり仕事にする必要はありません。
気軽な発信例:
- noteやブログに「AIで書いてみた日記」を投稿
- SNSで「ChatGPTで文章練習中」と発信
- 文章をまとめて、自分だけの練習ノートに保存
書くことを”習慣”にしておくと、文章の流れをつかむ感覚が早く身につきます。
実際の活用シーン
AIを使って完成した文章は、さまざまな場面で活用できます。
- SNS投稿:Instagram、X(旧Twitter)、Facebookなどの投稿文
- ブログ記事:note、アメブロ、WordPressブログ記事
- 仕事:メール文、簡単な報告書、クライアントへの提案書の構成
- プライベート:お礼状、挨拶文、イベント案内、PTAなどの連絡文
まずは気軽に、SNSの投稿文から試してみましょう。
AIライティングを続けるコツ
AIライティングを上達させるには、続けることが大切です。ここでは、挫折せずに楽しく続けるためのコツを紹介します。
完璧を目指さない
最初から上手に書こうとしなくて大丈夫。まずはAIに指示を出すことを優先させましょう。毎日少しずつ書き続けることで、文章の流れをつかむ感覚が早く身につきます。完璧な文章より、続けることが大切です。
AIの出力に自分の色を加える
AIの文章をそのまま使うのではなく、あなたらしさを加えましょう。例えば、自分の体験談を1文追加する、口調を変えてみる、具体的な数字や固有名詞を入れるなど。
AIは”考えるきっかけ”をくれる存在です。使いこなすうちに、あなた自身の文章力も確実に育っていくでしょう。
書く目的を明確にする
「何のために書くのか」を意識すると、AIへの指示も具体的になります。いきなり難しく考えず、“自分がどんな場面で文章を書きたいか”をざっくり決めておきましょう。
次のような目的が考えられます。
- 情報発信(ブログ・SNS):特定の読者に向けて、自分の体験や考えを発信する。
- スキルアップ・学習:AIを使って文章を整える練習や知識をまとめるための要約を作る。
- 在宅ワーク・副業:将来的に仕事に繋がるような、ライティングスキルを磨く。
- 日記・記録:日々の出来事や感じたことを整理し、振り返りや気づきに活かす。
書く目的が明確になると、AIへの指示(プロンプト)も出しやすくなり、何を書くべきかと迷う時間がぐっと減ります。
AIライティングの注意点
AIライティングは便利ですが、守るべきルールもあります。特に著作権や情報の正確性については、正しく理解しておくことが大切です。AIを安心して活用するために、押さえておくべき注意点をまとめました。
著作権に留意する
AIが生成した文章自体には著作権はないとされています。ただし、既存の文章をそのままコピーした場合は、著作権侵害になる可能性があります。必ず自分の言葉で修正・追加することが大切です。
AIはインターネット上のさまざまな文章を学習しているため、既存の表現と似た文章を生成することがあります。必ず自分で手を加えてから使うようにしましょう。
情報の正確性を確認する
AIの回答は鵜呑みにせず、必ず確認しましょう。 AIは時々、事実と違った情報を生成することがあります。これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。特に重要な情報は、企業の公式サイト、国や自治体が運営する公的機関のサイトや専門書など、信頼できる情報源で確かめること(ファクトチェック)が重要です。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 数字や統計データ | 出典が明記されているか、データが最新かを確認(公的機関のサイトで検索するのがおすすめ) |
| 固有名詞 | 企業名や商品名、人名が実在するか、正式名称と一致しているかを確認(AIは架空の名前を作ることがある) |
| 最新情報 | AIの学習データは古い場合がある。ニュースサイトや企業の公式サイトで最新情報を確認する |
| 専門的な内容(医療、法律、技術など) | 人の健康や権利に関わる内容は、必ず専門家の監修や信頼できる専門サイトで確認 |
AIに任せすぎない
AIはあくまでも補助ツールです。著作権や情報の正確性に注意しながら、最終的な判断は自分で行うことが大切です。
AIには、あなた自身の体験や感情、考え方の深みまでは表現できません。オリジナルの経験や視点を加えることで、文章に“あなたらしさ”が生まれます。
AIにすべてを任せるのではなく、「考えを整理してくれる相棒」として上手に活用していきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. AIツールはどれが良いですか?無料ツールでも大丈夫ですか?
A. まずは無料で使える汎用ツールから試してみるのがおすすめです。
最も手軽なのはChatGPT(無料版)です。文章の構成を考えたり、アイディアを出したり、リライトの練習をしたりと、基本的なAIライティングの流れを体験できます。
まずは無料版でAIライティングの感覚を掴んでから、必要に応じて有料版を検討しましょう。
Q2. AIにどのように指示すれば、良い文章が生成されますか?
A. AIへの指示は、具体的であるほど精度の高い文章が返ってきます。
「〇〇について教えて」と指示するよりも、「〇〇というテーマで、初心者向けにわかりやすく説明してください。」のように、目的や読者層を明確に伝えると、より適切な文章になります。
また、「あなたはプロのライターです」「マーケティング担当者として書いてください」といった役割を与えるのも効果的です。
一度で完璧な回答を求めず、何度かやり取りしながら「もう少し短く」「この部分を詳しく」と調整していくことで、理想の文章に近づきます。
Q3. AIが作った文章をそのまま使っても大丈夫ですか?
A. AIが作った文章をそのまま使うのは避けましょう。最終的な確認と修正は、必ず人の手で行います。
AIは誤った情報(ハルシネーション)を作り出すことがあります。特に数字や固有名詞、専門的な内容は、信頼できる情報源で確認することが大切です。また、AIの文章は他のコンテンツと似る傾向があります。自分の意見や体験を加えてオリジナルティを高めましょう。
AIの文章をそのまま使うと、オリジナリティがなく、情報の誤りにも気づけません。
Q4. どれくらいで上達しますか?
A. 個人差はありますが、毎日少しずつ使えば、1〜2週間で基本的な使い方に慣れます。1ヵ月続ければ、自分なりの活用法が見えてくるでしょう。
まとめ|まずは「1文書いてみる」からスタート
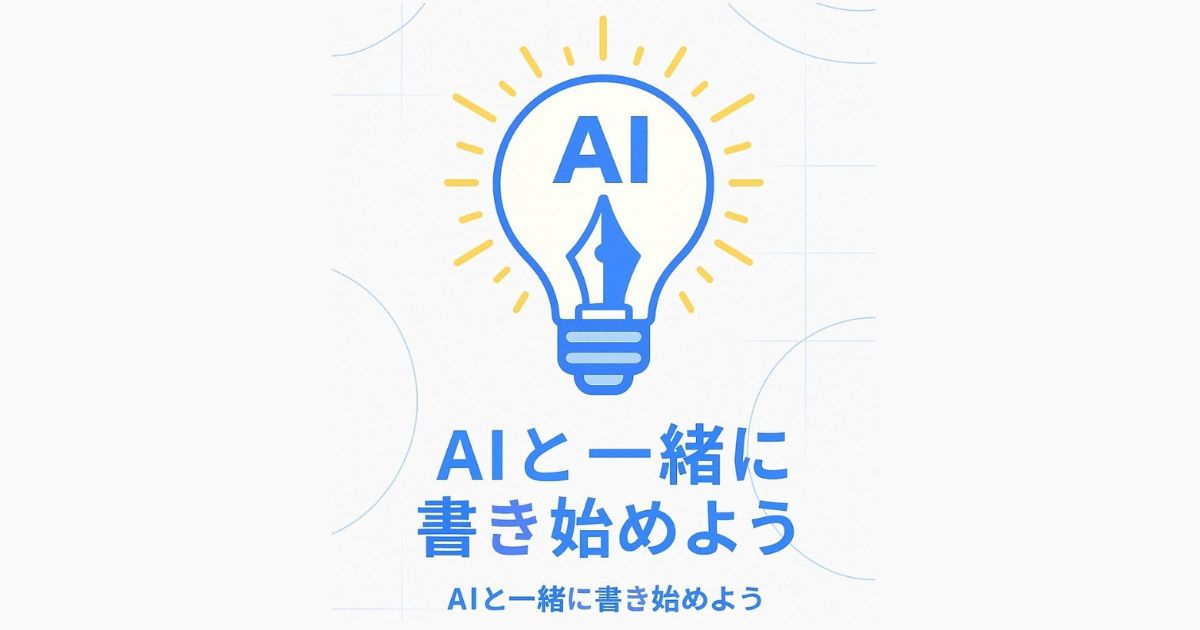
AIライティングを始めるために、特別な知識やスキルは必要ありません。ChatGPTに登録し、身近なテーマで練習を重ね、自分の言葉で仕上げる。この3つのステップを実践すれば、誰でもAIを活用した文章作成が可能です。完璧を目指さず、まずは1文書いてみましょう。今日からAIを相棒に、あなたらしい文章を作っていきませんか。