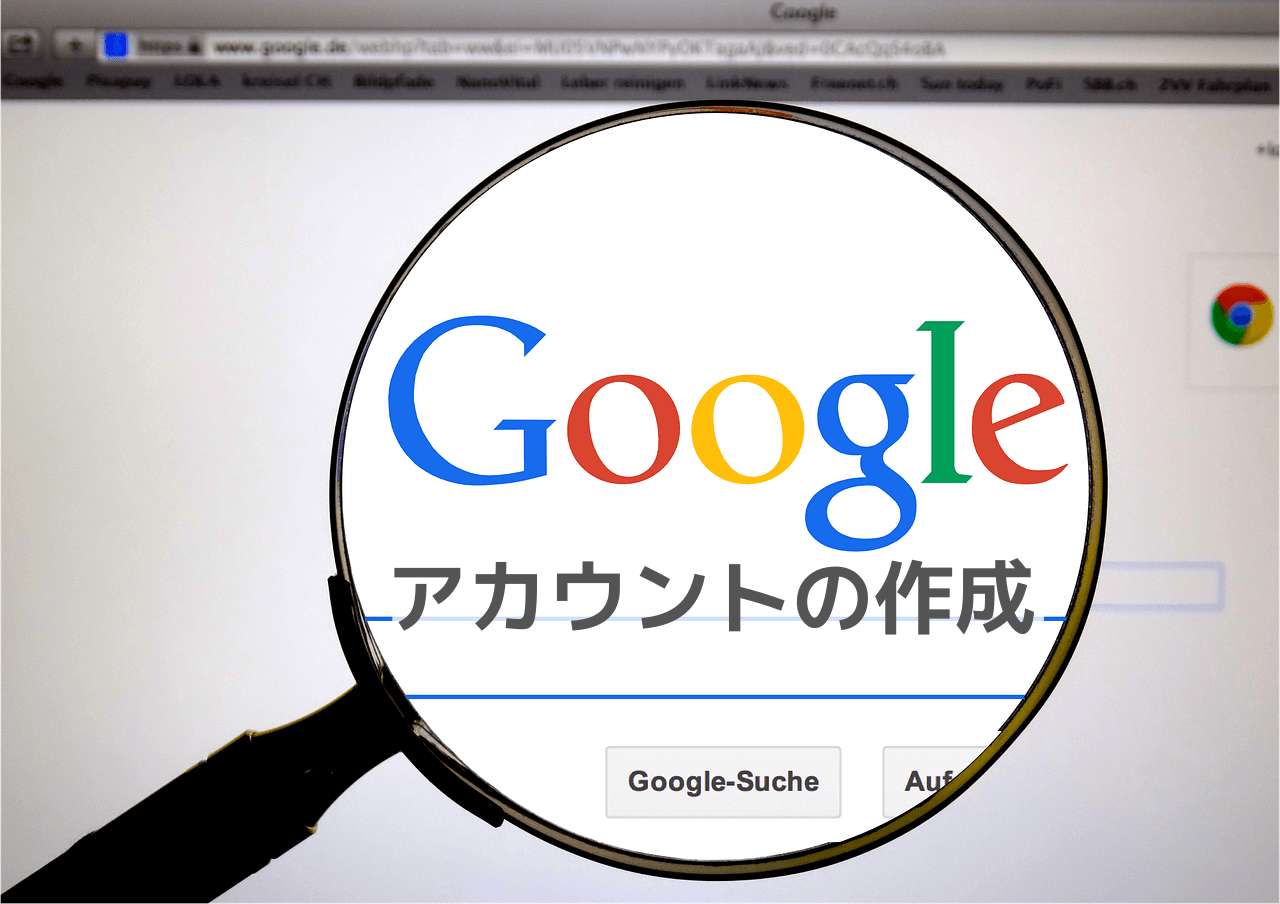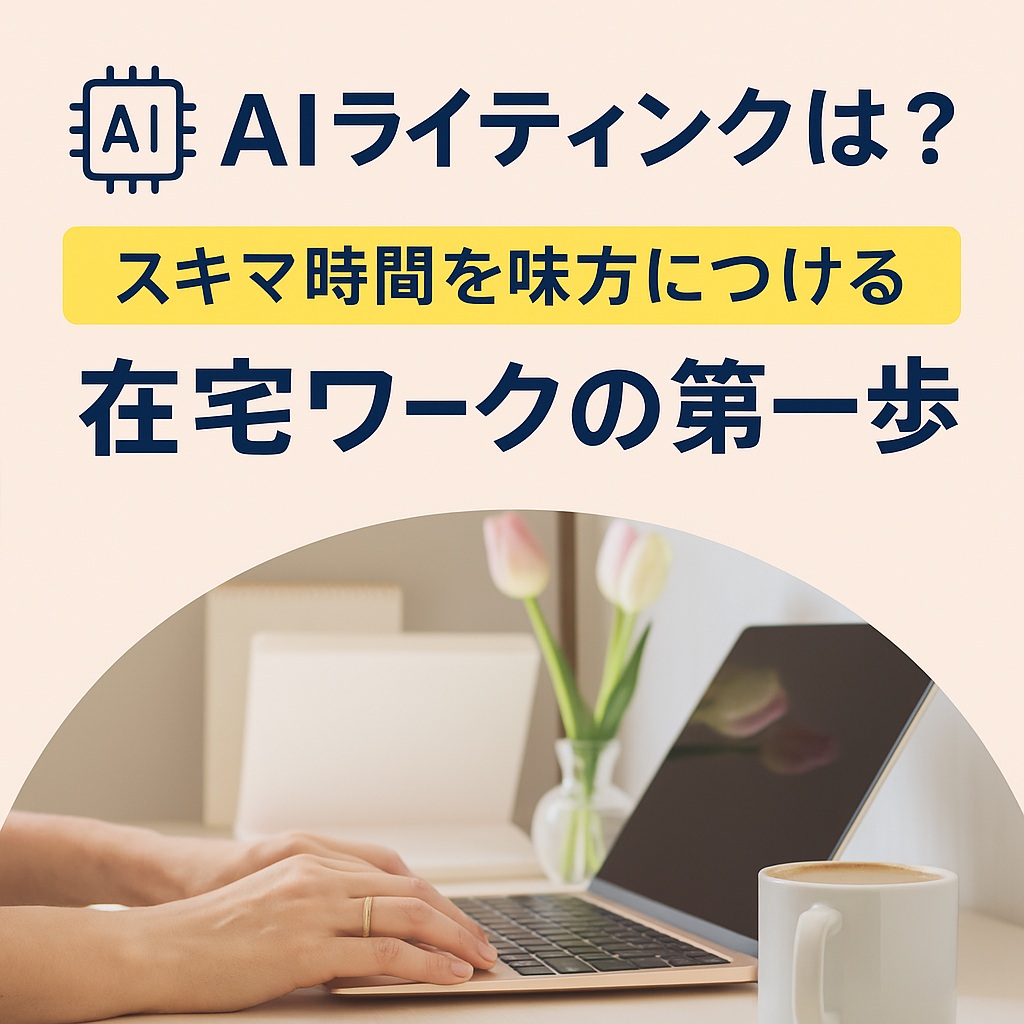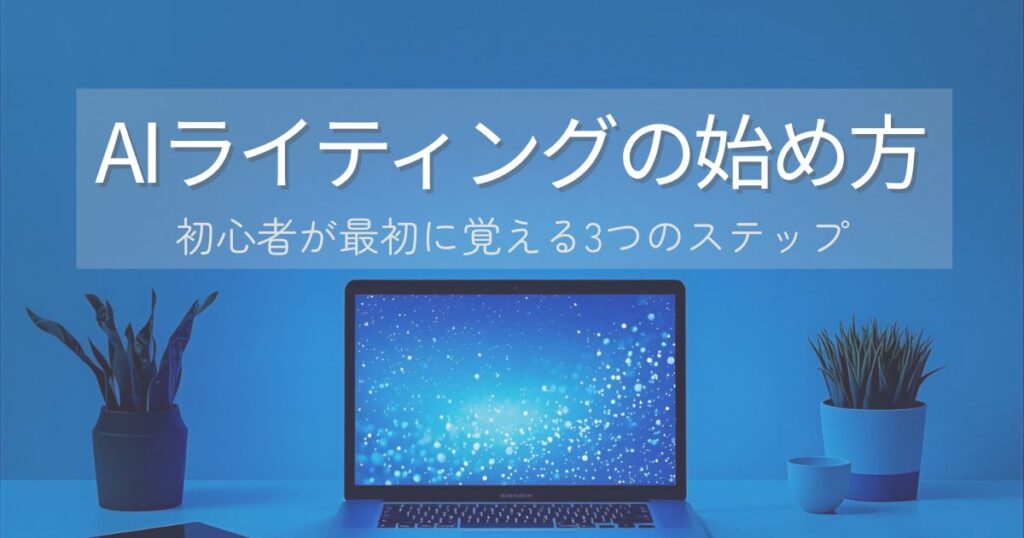ブログを始めてみたいけど、「文章を書くのが苦手」「記事を書く時間がない」などと悩んでいませんか? AIツールを使えば、隙間時間を活用して簡単に記事を作成できるようになります。この記事では、初心者の方がChatGPTだけで今すぐ始められるAIライティングの基本を解説します。
AIライティングのやり方とは?
AIライティングは、AI(人工知能)が文章作成をサポートしてくれる仕組みです。難しい専門知識は不要。ChatGPTなどのツールを使い、記事の構成から本文まで自動で生成できます。
AIライティングとは?ChatGPTでできること
AIライティングとは、AIに指示を出すことで自動的に文章を生成する技術のことです。ChatGPTを始めとするAIは、インターネット上の膨大な文章データを学習しています。この学習データをもとに、私たちが与えたプロンプト(指示文)に沿って、文章を生成できます。
AIを使えば、以下の作業を自動化・効率化できます。
- ブログ記事の見出し構成の作成
- 各見出しに対応する本文の執筆
- 記事タイトルや記事の概要の提案
- 既存の文章のリライトや要約
- SNS投稿文やメール文の作成
AIは、人間が「考える」部分をサポートしてくれます。ですがAIにすべてを任せるのではなく、AIが作った下書きに自分なりの表現を加えていくのが上手な活用法です。
主婦・初心者でもAIで記事が書ける理由
「文章を書くのが苦手」「専門的な知識がない」と不安に思う方も、AIライティングなら大丈夫。主婦や初心者にこそ、AIライティングがおすすめの理由は次の3つです。
- 構成に悩まずに済む
記事の骨格となる構成案をAIが提案してくれるので、「何を書けば良いか」と悩む時間がなくなります。 - スキマ時間で書ける
家事や育児、仕事の合間のわずかな時間でも、AIが作成した下書きを修正するだけで記事が進みます。 - リサーチの負担が減る
慣れないジャンルの記事でも、AIが基本情報を瞬時にまとめてくれるため、リサーチの負担が激減します。
AIライティングで得られるメリットと注意点
AIライティングの最大の魅力は、執筆時間を大幅に短縮できることです。構成から本文まで自動生成できるため、1日に複数記事を作成することも可能になります。さらに、AIが提案する言い回しを参考にすることで、自分の語彙や表現力の幅を広げられます。
一方で、AIを使う際には次のような注意点もあります。
- 誤情報(ハルシネーション)の可能性 最新情報に弱い場合があるため、必ず事実確認を行いましょう。
- 文体の不自然さ 語尾が単調、主語が省略されるなどの傾向があります。
- オリジナリティの欠如 AI任せにすると他の記事と似たような内容になりがちです。自分の経験を加えて差別化を。
AIは「優秀なアシスタント」として使うのが基本です。AIの出力をそのまま使わず、自分の目で最終確認・修正を加えましょう。
H2:ChatGPTを使ったAIライティングの始め方
AIライティングは、無料ツールから始めましょう。初心者におすすめのChatGPTを例に、登録方法から基本的な使い方までを解説します。
ChatGPTの登録方法からすぐ始める手順
ChatGPTは、開発元であるOpenAIの公式サイトから誰でも無料で始められます。
- 公式サイトにアクセス
「ChatGPT」で検索し、OpenAIの公式サイトにアクセスします。 - アカウント作成(Sign up)
メールアドレスと任意のパスワード、またはGoogleアカウントやApple IDを使って登録します。 - ログイン
登録後、ログインしたらチャット画面が表示されます。
ChatGPTには無料プランと有料プランがあります。無料プランでも、文章作成やリライトなどの基本機能が利用できます。プランは後から変更できますので、最初は無料プランを使って ChatGPT に慣れていきましょう。
Googleアカウントをお持ちでない方は、画像つき解説もどうぞ。
メGoogleアカウントの作成方法を初心者向けに4ステップで解説。Gmail・ドライブ・ChatGPT連携にも使える基礎知識を画像付きで紹介します。
ChatGPTの基本操作
ChatGPTの使い方はとてもシンプル。
- チャット画面にテーマや質問を入力
- AIが回答を出力
- 出力内容を確認して修正や加筆
質問→回答→調整の3ステップを繰り返すことで、自然な文章が完成します。最初の回答が思い通りでなくても大丈夫。「もっと優しい口調で」「具体例を3つ追加して」といった追加の指示を出して、内容を調整できます。最初から完璧を目指さず、まずはAIに書かせてから調整する方が効率的です。
初心者におすすめの練習テーマ
AIライティングに慣れるまでは、自分の得意分野や身近なテーマから選んで練習していきましょう。
主婦の方なら、家事の時短術や掃除のコツ、子育て中の悩みや体験談など。家計管理や節約などの生活アイディアも素敵です。
自分の身近な分野なら、AIが出力した文章を評価・修正しやすく、自然と使い方が身につきます。慣れてきたら、徐々に専門的なテーマにも挑戦していきましょう。
AIライティングを成功させる「プロンプト」の基本
AIに自分の意図を正しく伝えるには、指示文(プロンプト)の書き方がポイントです。同じテーマでも、プロンプトの出し方で文章の質や方向性は大きく変わります。効果的なプロンプトの基本構造とコツを紹介します。
プロンプトの基本構造(目的・指示・条件)
プロンプトとは、AIに対する指示文のこと。曖昧な指示では期待通りの結果は得られません。AIに的確な指示を出すには、目的・指示・条件の3つの要素を意識して伝えるのがコツです。
「目的」で何のために書くのかを明確にし、「指示」で具体的な内容や構成を示します。最後に「条件」で文字数・トーン・出力形式などを指定すると、狙い通りの文章を生成できます。
悪い例と改善例でわかる!プロンプトの作り方
プロンプトの良し悪しを理解するために、実際の例を比較してみましょう。
❌ 悪い例1 「家事について書いて」
このプロンプトでは情報が不足しています。AIは何について書けばいいのか迷ってしまい、一般的で浅い内容しか生成できません。
✅ 改善例 「共働き夫婦向けに、平日の夕食準備を30分で終わらせる時短レシピと段取り術について、1500文字程度のブログ記事を書いてください。具体的なレシピを2つ含めてください。」
ターゲット(共働き夫婦)、テーマ(夕食準備の時短)、文字数(1500文字)、盛り込む内容(レシピ2つ)が明確になっています。
❌ 悪い例2 「子育ての記事の構成考えて」
✅ 改善例 「2〜3歳のイヤイヤ期に悩む親向けに、対処法をまとめたブログ記事の構成(H2見出し5つ、各H2にH3を2〜3個ずつ)を作ってください。実践的なテクニックと心構えの両方を含めてください。」
具体的に指示することで、AIの出力精度は格段に向上します。
AIに人間らしい文章を書かせるポイント
AIが生成する文章は、時として機械的で冷たい印象を与えることがあります。自然で人間らしい文章に近づけるためには以下のポイントを意識しましょう。
ポイント1. 体験談や感情を含めるよう指示する
「実際に試した人の体験談風に書いてください」「読者に共感してもらえるよう、悩みを代弁する文章から始めてください」など、感情面を意識した指示を加えます。
ポイント2. 口語表現を使うよう依頼する
「です・ます調で、やさしく語りかけるような口調で書いてください」「難しい言葉は使わず、友達に話すような感じで」のように指定すると、親しみやすい文章になります。
ポイント3. 具体例やエピソードを求める
「具体的なシーンや例を3つ以上入れてください」と指示することで、読者がイメージしやすい文章が生成されます。
ポイント4. 文末のバリエーションを指定する
「〜です。〜ます。という語尾が続かないように、『〜なんです』『〜ですね』『〜でしょう』なども使ってください」と伝えると、単調さが解消されます。
以上のように指示することで、AIは文のトーンを変え、自然で温かみのある文章を生成できます。
実践!ChatGPTで記事を書く手順
ここからは、実際に記事を1本仕上げるまでの流れをステップ形式で解説します。テーマ設定から構成作成、リライト、公開までの一連の流れを押さえれば、AIを使った執筆が一気にスムーズになります。
ステップ1. 読者とテーマを決める
まずは、「誰に」「何を」伝えたいのかを明確にします。
文章を書くときに一番大切なのは、読者を思い浮かべて書くことです。例えば、家事を効率化したい主婦、在宅で仕事を始めたい人など。読む人の姿を具体的に想像すると、自然とテーマが絞りやすくなります。
読者が決まったら、その人にどんなことを伝えたいのか、テーマを考えます。自分の経験や気づきを交えて、「役に立つ」「励まされる」「読んでよかった」と思える内容を選ぶのがポイントです。
テーマを決めるときは、次の3つを意識してみましょう。
- 読者の悩みや疑問を解決できる内容か
- 自分の体験や意見を加えられるか
- 一言で言える、わかりやすいテーマになっているか
この段階で、読者とテーマがはっきりすれば、AIへの指示(プロンプト)もスムーズに出せるようになります。
ステップ2. ChatGPTに構成を作ってもらう
読者とテーマが決まったら、次は記事の骨組みとなる構成をAIに作ってもらいます。構成は見出し(H2)と小見出し(H3)で記載すると分かりやすいでしょう。
構成生成のプロンプト例
『家事 時短 テクニック』というテーマで、働く主婦向けのブログ記事を書きます。以下の条件で記事構成(H2見出しとH3見出し)を作ってください。
#条件
H2見出しを5〜7個
各H2の下にH3見出しを2〜3個ずつ
読者が実践しやすい具体的な方法を含める
導入→基礎知識→実践方法→応用→まとめの流れで構成するこのように指示すると、AIは記事全体の構成案を提示してくれます。
気に入らない部分があれば、「H2の3番目をもっと具体的にしてください」「H3を1つ追加してください」など、修正を依頼しましょう。納得いくまで調整することが大切です。
ステップ3. 本文を生成し、自然な表現に書き直す
構成ができたら、各見出しに対応する本文をAIに書いてもらいます。
本文生成のプロンプト例
以下のH3見出しに対して、300文字程度の本文を書いてください。
H3:朝の家事を15分短縮する段取り術
#条件
具体的な手順を3つ以上含める
実践しやすいように優しい口調で生成された文章はそのまま使わず、必ず読んで確認します。語尾の繰り返しや接続詞の単調さを調整し、自分の言葉で言い換えましょう。
ステップ4. タイトルを整える
記事本文が完成したらタイトルを作成します。タイトルは、読者をひきつけるために最も重要な要素です。
タイトル作成のプロンプト例
以下のブログ記事のタイトル案を5つ作ってください。
記事内容:働く主婦向けの家事時短テクニック
メインキーワード:家事 時短
条件:
キーワードを自然に含める
30文字前後
クリックしたくなる魅力的な表現
数字や具体性を含めるAIが複数のタイトル案を提示してくれるので、その中から魅力的なものを選びましょう。複数の案の良い部分を組み合わせて、自分なりにアレンジするのもおすすめです。
ステップ5. 人間が確認、調節して読みやすくする
AIが作った文章は“たたき台”です。公開前に必ず確認し、人の手で読みやすさを整えます。
- 通読して引っかかりを修正する 言い回しの重複や主語抜けを修正、長文は分割
- トーンをそろえる 語尾が続くときは言い換え、やさしい口調で統一
- オリジナルの要素を加える 体験談・具体例を1点加えて“自分の記事”に
文章を整えたら、事実確認(ファクトチェック)を行います。数字や固有名詞、根拠の出典は誤りがないかを確認しましょう。次の章で、初めての人でも迷わないファクトチェックの手順を紹介します。
AIライティングのリスクを減らす「ファクトチェック」の基本
AIは便利ですが、もっともらしい誤りが混ざることがあります。トラブルを防ぐためにも、公開前の事実確認(ファクトチェック)が欠かせません。ここでは、ファクトチェックのポイントを説明します。
AI記事でチェックすべき4つの項目
AIが生成した文章の真偽を確認する際、特に以下の4つの項目を必ずチェックしましょう。
- 出典はあるか?
引用しているデータや情報源が示されているかを確認します。AIが情報源を提示しない場合、自分でGoogle検索などで裏付けを取ります。 - 情報は新しいか?
AIの学習データは最新情報ではない可能性があります。特に法律、制度、市場データなど日付が重要な情報は、最新のものかを必ず確認し、必要に応じて更新します。 - 一次情報で確かめられるか?
公的機関のデータ、企業の公式サイト、学術論文など、信頼できる情報源(一次情報)で内容の裏付けを確認します。 - 数字・固有名詞は正しいか?
「○○大臣」「○○年の法改正」「売上高○○万円」といった、具体的な数字や人名、企業名はAIが間違えやすい部分です。必ず検索して正確性を確認しましょう。
ChatGPTの「ミス」を防ぐプロンプトのコツ
ファクトチェックの手間を減らすには、文章を生成するChatGPTへの指示(プロンプト)を工夫するのが効果的です。AIが出力した後、再質問することで精度を高めましょう。
| 目的 | 再質問プロンプトの例 | 効果 |
|---|---|---|
| 出典の明確化 | 「この数字の出典(情報源のURL)を示してください」 | 根拠となるソースを明確にさせ、信頼性を高めます。 |
| 情報の鮮度確認 | 「この情報を最新日付に更新して説明し直してください」 | 古い情報のリスクを減らし、現在の状況に合わせた文章に修正できます。 |
| 断定の回避 | 「断定表現を弱めて(例:〜と言われています、〜の可能性があります)再提示してください」 | AIが事実ではないことを「〜です」と言い切るリスクを避け、誤情報を断定する事態を防げます。 |
情報が不明確な場合の対処法
Web検索や検証をしても、情報源が複数あるなどで判断に迷うことも出てきます。そのような場合には以下のように対処すると良いでしょう。
- 断定を避ける 「~とされます」「〜の可能性があります」といった表現に和らげます。
- 保留にする 確証が持てない情報は無理に記事に含めない判断も大切です。根拠が得られてから追記します。
- 後日更新を前提に書く 制度改正など、今後情報が更新されることが確実な場合は、「※最新情報が確認でき次第、更新します」など明記しておきます。
AIライティングを自然に仕上げるコツ
AIが生成した文章は、そのままでは不自然で冷たい印象を与えることがあります。AIの文章を人間らしく、読みやすく仕上げるテクニックを紹介します。
AIの文章が不自然になる原因と修正法
AIの文章が不自然になる主な原因は、語彙や表現の単調さにあります。
| AI文章の不自然さ | 修正法 |
|---|---|
| 同じ語尾の繰り返し | 語尾(〜です、〜ます、〜でしょう)のパターンを増やす 「〜ね」「〜だ」など親しみやすい口調も織り交ぜる |
| 接続詞の種類が少ない | 「そして」「また」「しかし」以外の接続詞(例:加えて、その一方で、とはいえ)に置き換えてリズムを変える |
| 文の調子が単調 | 読者の立場に寄り添う共感の言葉や、呼びかけの表現を加える |
| 主語の省略 | 文脈が曖昧にならないよう、主語を明確に補う |
構成はAIに任せ、内容は自分で加筆する
AIの効果的な使い方は「構成作成はAI、本文執筆は人間」というハイブリッド方式です。
まず、AIに記事の「骨格」(構成)を作らせます。 AIにテーマや検索意図を伝え、H2、H3の見出し案を出力させましょう。続いて、人の手で本文を肉付けします。 AIが出力した下書きを参考にしつつ、自分の経験談、失敗談、独自の視点など、AIには書けない一次情報をメインに加筆・修正します。
AIと人間のハイブリッド方式で執筆時間を短縮しつつ、読者に響くオリジナリティの高い記事が書けます。
「AIっぽさ」を消す言い換え実例
AIが生成した文章を、人間らしい自然な表現に変える具体例を紹介します。修正前・修正後で比較して違いを見ていきましょう。
例1. 語尾の調整
❌ AI生成文
「この方法は効果的です。多くの人が実践しています。結果が出やすいです。」
✅ 修正後
「この方法は効果的なんです。多くの人が実践し、結果も出やすいですよ。」
「です」の繰り返しを避け、「なんです」「〜し、」でつなぎ、会話調に。
例2. 堅い表現を柔らかく
❌ AI生成文
「当該の手法を実施することにより、業務効率が向上します。」
✅ 修正後
「この方法を試してみると、作業がぐっと効率的になります。」
「当該」「実施」「向上」といった堅い言葉を、日常的な表現に置き換えました。
例3. 主語と接続詞の調整
❌ AI生成文
「AIライティングは便利です。しかしAIライティングには注意点もあります。また、AIライティングを使う際は確認が必要です。」
✅ 修正後
「AIライティングは便利ですが、注意点もあります。使う際は必ず内容を確認しましょう。」
繰り返される主語を削除し、接続詞も整理して簡潔にしました。
例4. 感情表現を加える
❌ AI生成文
「この方法は時間短縮に有効です。」
✅ 修正後
「この方法を使うと、驚くほど時間が短縮できます。私も初めは半信半疑でしたが、試してみて本当に助かりました。」
事実だけでなく、感情や体験を加えることで、読者の共感が得やすくなります。
例5. 具体性を持たせる
❌ AI生成文
「野菜を多く摂取することが重要です。」
✅ 修正後
「1日に小鉢5皿分の野菜を摂るのが理想とされています。とはいえ毎日は難しいですね。私はスムージーで2〜3皿分をまとめて摂るようにしています。」
抽象的な表現に具体的な数字と実践例を追加し、イメージしやすくしました。
このように修正を加えることで、AIの文章を「あなたらしい文章」に変えられます。
AIライティングを学び続けるためのコツ
AIツールは日々進化しています。一度AIの使い方を覚えたら終わりではありません。継続的に学び、スキルを磨いていくことが大切です。初心者でも無理なく続けられる学習習慣をご紹介します。
無料で学べる講座や動画を活用する
プロンプトのコツやツールの最新機能は、YouTubeなどの動画コンテンツで学ぶのが効率的です。「ChatGPT プロンプト」「AI ライティング」といったキーワードで検索し、実際に記事作成のプロセスを見せてくれるチャンネルを選びましょう。
「プロンプトの基本構造」など基礎を解説している動画を一本選んでみて、実際に手を動かしながら視聴するのがおすすめです。
自分だけの「プロンプト集」を作る
実際にやってみて「良い記事が書けた」「期待通りの答えが返ってきた」プロンプトは、ノートやNotionなどのツールに保存しておきましょう。
このような「成功プロンプト集」を作っておけば、良いプロンプトを再利用できて記事作成のたびに一から指示を考える手間がなくなります。また、蓄積したプロンプトを分析することで、「なぜこの指示でうまくいったのか」というプロンプト設計の本質的なスキルが磨かれます。
良いプロンプトは、あなたのAIライティングを支える大切なノウハウ資産となります。
1日5分から!毎日のAI活用を習慣化する
AIの活用は、少しずつで大丈夫。気負いすぎず、まずは1日5分程度の小さな習慣から始めてみましょう。
- 軽い課題を決める
「今日はSNSの投稿文の下書きを作らせる」「過去記事のタイトル案を5パターン作らせる」など、すぐにできる課題を決めます。 - 実行して記録する
AIに指示を出して、結果を記録します。 - 振り返る
週末に「どんなプロンプトがうまくいったか?」を軽く振り返ります。良いものは「成功プロンプト集」に保存します。
この3ステップを繰り返せば、数ヵ月後にはAIを使いこなすスキルが身についているでしょう。
まとめ|AIライティングで “時間”も“文章力”も手に入れよう
AIライティングは、ChatGPTなどのAIツールを使って誰でも始められる書き方です。大切なのは、出力をそのまま使わず、プロンプトで意図を伝え、人の手で確認・調整すること。毎日少しずつ練習し、うまくいった指示文を「成功プロンプト」として蓄積すれば、短い時間でも質の高い記事が作れます。今日からAIを相棒に、時間も文章力も手に入れていきませんか。