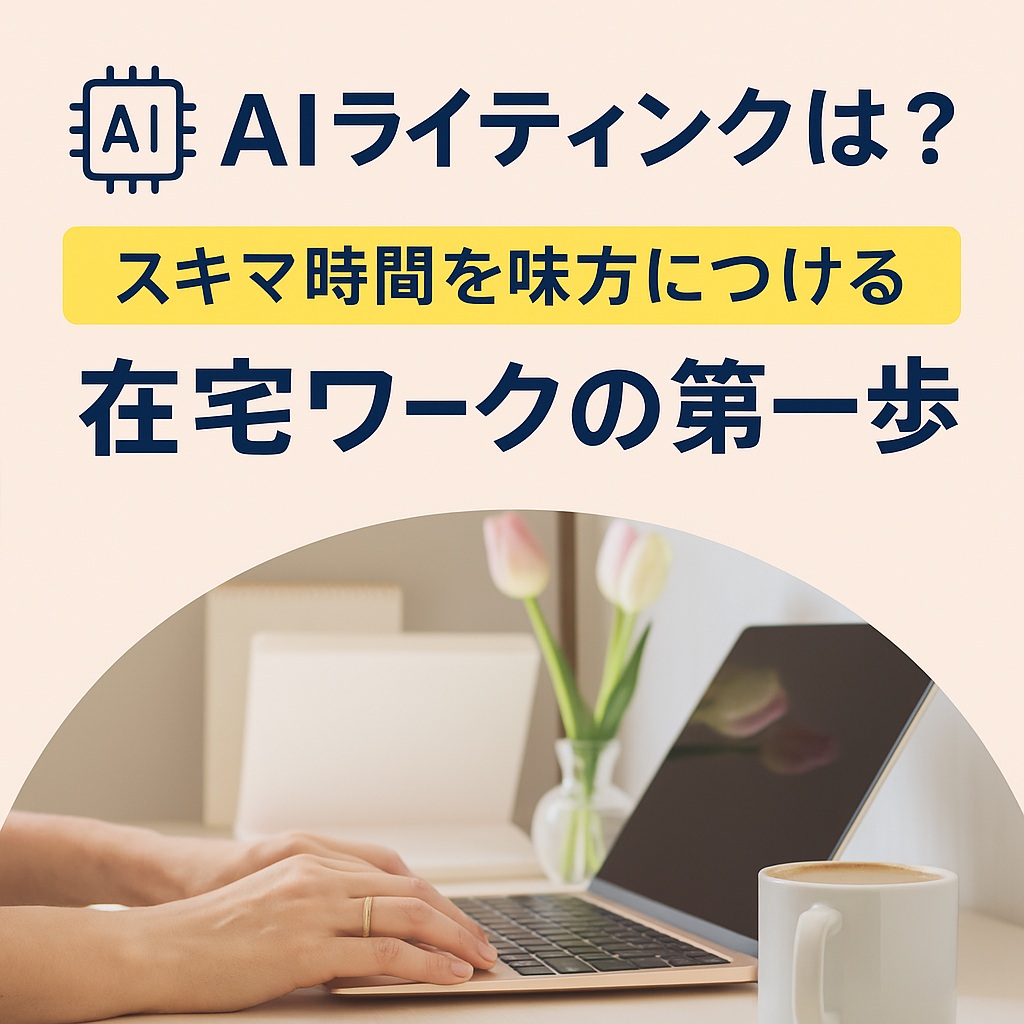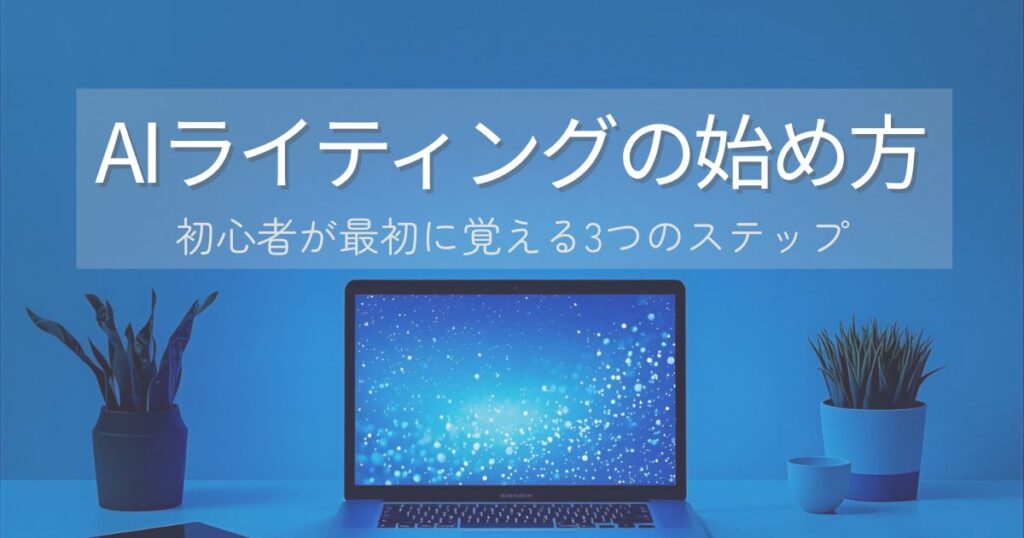「記事作成にChatGPTを活用したいけれど、どう使えばいいのか分からない」と悩んでいませんか?
本記事では、ChatGPTに渡すプロンプト(指示文)を基本の4つの要素(目的・条件・形式・質問ルール)に整理しました。この4つを押えるだけで出力のブレが小さくなり、作業が速くなります。そのままコピペできる形式でまとめているので、保存して記事作成に活用してください。
※ 本記事のプロンプトはコピペOK。必要なものだけ使い、目的・条件・形式・質問ルールを作業に合わせて調整してください。
ChatGPTへの質問(プロンプト)入門:基本の4つ
ChatGPTに質問するときは、1. 目的 →2. 条件 →3. 形式 の順で伝えると回答がぶれにくくなります。さらに、4. 不足があれば先に質問してもらうルールを足すと、確認漏れを防げます。
1. 最初に目的を伝える
何を求めているのか、最初にハッキリと伝えましょう。
ChatGPTは目的があいまいだと、どんな方向に進めばよいか判断できません。「要約したい」「構成案がほしい」「本文を書いてほしい」など、ゴールを一言で明確にするのがコツです。
場合によって「どんな立場・専門性で答えてほしいか」も添えるとより安定します。たとえば「あなたはSEOライターです」「主婦向けにやさしく説明してください」などと指定すると、回答のトーンや視点が揃いやすくなります。
【コピペ用プロンプト】2. 条件や制約を添える
次に、どんな前提や制約があるかを伝えましょう。
読者のレベルや文字数、使ってほしくない言葉などを最初に伝えることで、後からの修正が減ります。
「初心者向け」「専門用語を使わない」「200〜300字で」など、作業の枠を明確にしましょう。
3. 出力形式を指定する
どんな形で答えてほしいかを明示します。同じ内容でも、箇条書き・表・文章など、形式を変えるだけで読みやすさが大きく変わります。
ブログ記事では「H2:大見出し/H3:小見出し」という構造が基本です。見出しの階層を意識して指示すると、文章の流れが整理され、後からコピペして使いやすくなります。
「H2/H3の見出し+箇条」「2列の表」「3段落の短文」など、最終形を具体的に伝えるのがポイントです。
【コピペ用プロンプト】4. 不足があれば先に質問してもらう(確認ルール)
前提が足りないまま出力すると、方向違いの文章になるかもしれません。「必要な情報が足りないときは、先に質問してから書いてください」と伝えておきましょう。
ChatGPTに“考えてから書く”よう促すことで、やり直しの手間がぐっと減ります。
一括テンプレート(コピペOK)
【コピペ用プロンプト】条件:{読者・字数・禁止事項など}
形式:{見出し・箇条・表など}。
不足があれば先に質問してから出力してください。
この4つを意識するだけで、ChatGPTはあなたの意図を正確に理解し、ライティングのパートナーとして安定して働いてくれます。
次章では、この型を使った作業別の質問例を紹介します。
【作業別1】アイデア出しに使える質問
記事を書き始める前に、まずは「どんなテーマで、どんな切り口にするか」を整理しましょう。ChatGPTに質問することで考えがまとまり、記事構成のスタート地点が明確になります。
記事のテーマ候補を広げる
【狙い】執筆の出発点をすばやく作る
【使い方】キーワードを渡し、重複を除外+字数指定で短く量産
読者の悩みを洗い出す
【狙い】検索意図からズレないようにする
【使い方】読者像を一言で伝え、短文・重複なしで列挙
ターゲットの行動を想定する(検索前→検索後)
【狙い】導入や結論の方向性を定める
【使い方】検索前の状態と、記事を読んだ後の変化を対で整理
関連テーマを広げる
【狙い】今後の記事テーマを派生させる
【使い方】現在のテーマから、関連カテゴリを広げて提案
書く優先順位をつける
【狙い】ネタが多すぎるときに、着手順を整理する
【使い方】想定読者・需要・専門性の3軸で並べ替え
テーマ一覧:{貼り付け}
ChatGPTに「テーマを広げる/読者の悩みを洗い出す/行動を想定する」といった質問を投げることで、構成を考える前の“下ごしらえ”が整います。
次章では、このアイデアをもとに見出し構成を作るプロンプトを紹介します。
【作業別2】構成・見出し作成に使える質問
テーマ決定後、記事の構成(H2:大見出し/H3:小見出し)を考えます。見出しを整理することで、全体の流れが明確になり、書きやすさが一気に上がります。ChatGPTを使えば、短時間で“骨組み”を整えることができます。
記事の骨組み(H2:大見出し/H3:小見出し)を作る
【狙い】章立てを先に決め、後工程のムダを減らす
【使い方】H2は5〜7個、各H2にH3を2〜3個。最後に抜け確認
#条件
・H2(大見出し)は5〜7個
・各H2の下にH3(小見出し)を2〜3個
・初心者向け
・冗長な表現は避ける
・見出し同士の重複は除外
導入文(リード文)の下書きを作る
【狙い】読者の検索意図を受け止め、本文へ自然につなぐ
【使い方】読者像→本記事の価値→読後の変化の順で180〜220字で。
見出しの重複・不足を点検する
【狙い】似た内容の整理と抜けの補完
【使い方】既存のH2/H3を貼り、統合・追加を指示
読者が迷わない順序に並べ替えて提示してください。
見出し:{貼り付け}
構成の流れをチェックする(読みやすさ確認)
【狙い】H2・H3の並びが自然かどうかを確認
【使い方】見出し一覧を貼り、論理的な流れの改善を依頼
見出し構成:{貼り付け}
構成案をタイトルと照らし合わせる
【狙い】見出しがタイトルの意図とズレていないか確認
【使い方】タイトルを渡して、構成との整合性をチェック
次の見出し構成がタイトルの意図に沿っているかを確認し、必要に応じて不足している視点を最大3つ追加してください。
見出し構成:{貼り付け}
構成づくりでは、ChatGPTに「H2とH3の階層を意識させる」「重複を整理させる」「タイトルと整合性を取る」ことが重要です。
次章では、完成した構成をもとに本文を作成・整形するプロンプトを紹介します。
【作業別3】本文作成・文章の整形に使える質問
構成が決まったら、本文を作成します。
ChatGPTに任せるときは、1段落の長さや口調などをあらかじめ伝えておくと出力が安定します。ブログやSEO記事では、「短い段落」「結論→理由→具体例」の流れを意識するのがポイントです。
本文の下書きを作る(短い段落で)
【狙い】先に大まかな下書きを作って、全体の流れをつかむ
【使い方】1段落=3〜5文、主語と述語を揃える
本文を箇条書きに要約する
【狙い】重要な部分を分かりやすく整理する
【使い方】結論→根拠→補足の順で3項目
順番は結論→根拠→補足です。
文章の口調・語尾を統一する
【狙い】記事全体のトーンをそろえる
【使い方】「です/ます」統一+冗長語の削除
専門用語は言い換え、固有名詞は仮名に。
本文:{貼り付け}
段落ごとの論理関係を整える
【狙い】自然な流れで読めるようにする
【使い方】「一方で」「つまり」「そのため」など、接続語を調整
接続語や主語の抜けがある場合は補い、意味を変えずに自然な流れに整えてください。
本文:{貼り付け}
文章を短く整える(200字前後)
【狙い】SNSやメタディスクリプションなど、短文用途に調整
【使い方】1文40字以内、200字前後でまとめる
1文は40字以内を目安に。言葉を削るのではなく、言い換えで自然に短くしてください。
本文:{貼り付け}
本文の整形は、「ChatGPTに書かせたあと、もう一度ChatGPTで整える」と考えるのがコツです。
次章では、こうして完成した記事をSEO向けに整えるプロンプトを紹介します。
【作業別4】SEO対策に使える質問
記事ができたら、検索結果でより多く読まれるようにSEO(検索エンジン最適化)を意識して仕上げましょう。SEOとは、Googleなどの検索エンジンで記事を上位に表示させるための工夫のこと。
初めは、タイトル・説明文(メタディスクリプション)・内部リンクの3つを整えるだけでも効果があります。ChatGPTを使えば、数分で案を出して比較検討できるため、効率的に改善できます。
記事タイトル案を作る(32文字目安)
【狙い】検索結果でクリックされやすいタイトルを考える
【使い方】キーワードを入れつつ、32文字以内・重複回避・自然な日本語を指定
・32文字以内
・タイトル同士が重複しない
・自然でわかりやすい日本語にしてください。
メタディスクリプションを作る(90〜120文字)
メタディスクリプションとは、検索結果のタイトル下に表示される記事の説明文のことです。PCでは約120文字、モバイルでは70〜80文字が表示されるので、前半に要点を入れるのがポイントです。
【狙い】検索結果で記事の内容を簡潔に伝える
【使い方】文字数90~120文字で、前半に要点を入れ初心者に伝わりやすく書く
・90〜120文字
・前半70〜80文字に要点を入れる
・初心者にも伝わりやすい自然な文にしてください。
内部リンクの候補を探す
内部リンクとは、同じサイト内の記事同士をつなぐリンクのことです。関連する記事をつなげることで、読者が他の記事も読んでくれやすくなり、SEO評価の向上にもつながります。
【狙い】関連記事をつなげて滞在時間を伸ばす
【使い方】自サイト内の記事タイトルやカテゴリを入力して提案を受ける
・同じテーマを扱うものを優先
・重複は除外
・タイトルと関連度を簡潔に説明してください。
記事タイトル一覧:{貼り付け}
【作業別5】SNS発信に使える質問
ChatGPTは記事本文はもちろん、SNS投稿やお知らせ文など、短い文章の作成にも役立ちます。読者に伝わりやすい言葉を選んだり、文章の雰囲気を整えたりするのにも活用できます。
X(旧Twitter)の投稿文を作る
【狙い】短く伝わるSNS文をつくる
【使い方】目的と文字数を指定して投稿案を出してもらう
・文章の冒頭に興味を引く一文を入れる
・ハッシュタグは2〜3個まで
・自然で読みやすい文体で
文体・口調をSNS向けに変える
【狙い】フォーマルな文章を、SNSで親しみやすい文体に変える
【使い方】元の文章を貼って「柔らかく」などの指定を添える
投稿に使える要約を作る
【狙い】長い文章をSNS向けに短くまとめる
【使い方】本文を貼り、文字数制限を指定する
重要な要点を落とさず、SNSで読まれるトーンにしてください。
本文:{貼り付け}
短文相談(思考整理やメモに)
【狙い】アイデア整理や企画メモとして活用する
【使い方】気づきを1行で書き、質問を促す形にする
ChatGPTをSNSに使うことで、「伝える練習」や「文章を磨く力」が身につきます。短い文章で読者の反応を見ながら改善していけば、記事のタイトル作りにも応用できるでしょう。
【最終チェック】記事公開前の確認リスト(コピペOK)
記事の完成後は、ChatGPTで最終チェックをしましょう。誤字脱字だけでなく、読みやすさや文章の一貫性も確認できます。以下のプロンプトを使って、公開前に必要な修正点をまとめて指摘してもらいましょう。
文章全体をチェックしてもらう
【狙い】誤字・文法・表記ゆれ・不自然な文を一括チェック
【コピペ用プロンプト】誤字脱字、助詞の重なり、表記ゆれ、不自然な語順があれば修正案を提示してください。
修正理由は簡潔で構いません。
本文:{貼り付け}
読みやすさを確認する
【狙い】リズム・文長・接続の自然さを整える
【コピペ用プロンプト】必要に応じて、自然な言い換え例も提案してください。
本文:{貼り付け}
タイトルと内容のズレを確認する
【狙い】タイトルに対して本文がずれていないか最終確認
【コピペ用プロンプト】もしズレがある場合は、見出しまたは文末の修正案を提示してください。
本文:{貼り付け}
見出し構成の整理
【狙い】H2(大見出し)・H3(小見出し)の流れとバランスを確認
【コピペ用プロンプト】・H2とH3の階層が正しく整理されているか
・内容の重複や抜けがないか
・自然な順序になっているか
見出し構成:{貼り付け}
まとめの整え方を確認する
【狙い】記事の締めが自然で印象に残るか確認
【コピペ用プロンプト】重複や抽象表現を避け、自然な言葉で終わるように調整してください。
まとめ文:{貼り付け}
丁寧に仕上げた記事ほど、最後の確認で印象が変わります。自分で気づきにくいミスのチェックはAIに任せ、より自然で読みやすい記事に仕上げましょう。
まとめ|ChatGPTを“書く相棒”として育てよう
ChatGPTをうまく使うコツは、はっきり伝えることと、使いながら調整することです。
最初は思いどおりの回答が得られなくても、「目的」「条件」「形式」「不足があれば質問してから」の4つを意識すれば、出力のブレはぐっと減り、記事づくりが安定します。
プロンプトは一度作って終わりではなく、自分の書き方に合わせて少しずつ育てていくもの。ChatGPTを”書く相棒”として使いこなし、ライティングの質を上げていきましょう。
✍️ 次回予告
次の記事では、今回紹介した基本型をもとに、実際に使える 「質問例(プロンプト)100選」 を紹介します。記事制作の現場でそのまま使える定番ばかりですので、保存して活用してください。